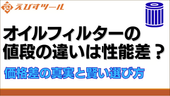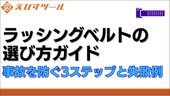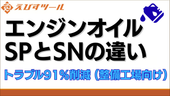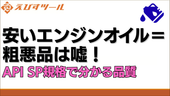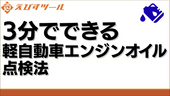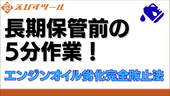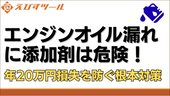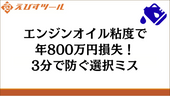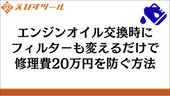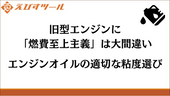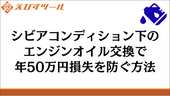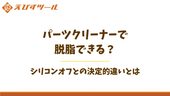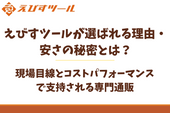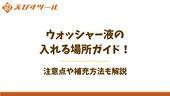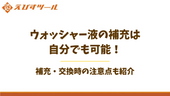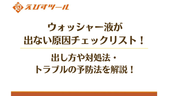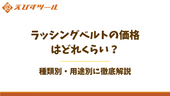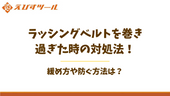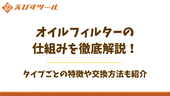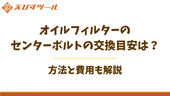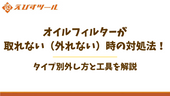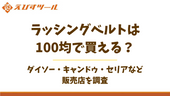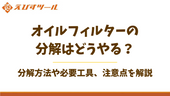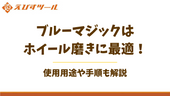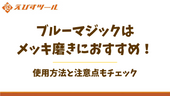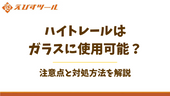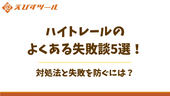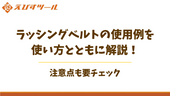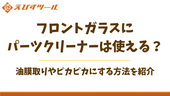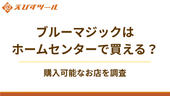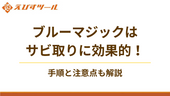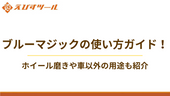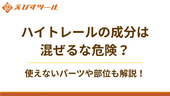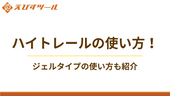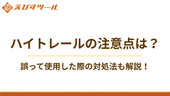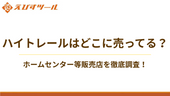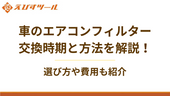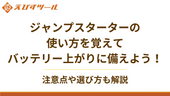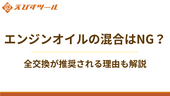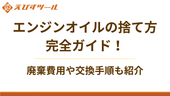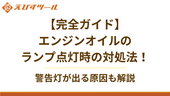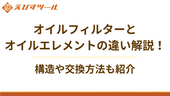「オイル交換をしたのに、3ヶ月でエンジンから異音がする。」
こういうクレーム、経験ありませんか?
もしくは、まだ経験していなくても「いつか言われるんじゃないか」という不安、感じていませんか?
実は、このクレームを受けた整備工場の多くが、同じ間違いをしています。それは「お客様の言う通りにした」ことです。
お客さんが「安く済ませたい」と言うから、言われた通りに安いオイルを入れた。でも、トラブルが起きたら結局こっちの責任にされる。理不尽だと思いつつ、これが現実なんですよね。
特に法人のお客様の場合、1台トラブルが起きると全車両の整備を他に移されるリスクがあります。年間で数百万円の取引が、たった一度のオイル選定ミスで消える可能性があるんです。
「お客様の言う通りにする」のではなく「お客様のためになる提案をする」
この違いを理解し、実践できれば、クレームを防ぎながら信頼と売上を高められます。この記事では、SPグレード100%化学合成油を法人のお客様にどう提案すればいいか、具体的な数字と方法をお伝えします。

整備工場が抱える「オイル提案」の3つの悩み
多くの整備工場が、似たような苦い経験をしていると思います。
想定される失敗ケース① 安いオイルを勧めて顧客を失う
お客様から「できるだけ安く」と言われて、安価な鉱物油を提案。半年後にエンジンの調子が悪くなり、「あの時のオイルのせいじゃないか」とクレームになる。
直接的な因果関係は証明できなくても、お客様の不信感は確実に残ります。法人の場合は特に、1台のトラブルで全車両の取引を失うリスクがあります。年間数百万円の取引が消える可能性を考えると、怖いところです。
想定される失敗ケース② 高性能オイルを提案できず信頼を失う
付き合いの長い法人顧客が、他の工場や知人から「SPグレードの化学合成油に変えたら調子いいよ」と聞いて、「なんでうちの工場は教えてくれなかったの?ずっと付き合いがあるのに」と言われる。
提案しなかったことが「知識がない」「客のことを考えていない」と受け取られ、長年の信頼関係が崩れる。こんな事態は避けたいですよね。
整備工場経営者が直面する「オイル販売」のジレンマ
「安いオイルばかり売っていたら利益が出ない。でも高いオイルを勧めたらお客様が離れるんじゃないか...」
多くの工場経営者が、このジレンマを抱えています。単価を上げたいけれど、お客様に嫌がられたくない。競合他社との差別化もしたいけれど、方法が分からない。
実は、SPグレード100%化学合成油は、このジレンマを解決する鍵なんです。お客様のコスト削減に貢献しながら、工場の利益も確保できる。この「Win-Win」の提案ができれば、顧客満足度も利益率も同時に改善できます。
SPグレード化学合成油の3つのメリット
お客様に説明するとき、「エンジンにいいですよ」だけでは不十分です。法人の担当者が稟議を通せるように、具体的な数値とコストで説明できることが重要になります。
メリット① オイル交換回数が半分になり、総コストが下がる
従来のSNグレード半合成油だと、業務車両の場合は5,000km〜7,000kmごとの交換が推奨されます。ところが、SPグレード100%化学合成油なら、優れた酸化安定性のおかげで10,000km〜15,000kmまで交換サイクルを延ばせるんですね。
年間20,000km走行する車両で比較してみると:
- SNグレード半合成油:年3〜4回の交換
- SPグレード100%化学合成油:年1〜2回の交換
交換回数が減れば、オイル代だけじゃなく交換工賃も削減できます。それと、意外と見落とされがちなのが、お客様の車両稼働停止時間が減ることです。配送業務をやっている法人なら、稼働時間の増加は売上に直結します。
お客様への説明例:
「今のオイルだと年4回交換で工賃込みで1台あたり年間1万6千円くらいかかってますよね。化学合成油なら年2回で済むので、年1万円くらい。それに、入庫回数が減るぶん、車の稼働時間も増やせますよ」
メリット② エンジントラブルを予防できる
SP規格は、API(米国石油協会)が2020年に導入した最新のガソリンエンジン用オイル規格です。従来のSN規格と比較して、性能が大幅に向上しています。
特に注目したいのがLSPI(低速早期着火)の防止性能です。最近増えているターボ車で発生するこのLSPI、エンジンに深刻なダメージを与えるんですが、SP規格はこれを防ぐ性能を持っています。
それから、摩耗防止性能とデポジット抑制性能も向上しています。国土交通省の自動車検査独立行政法人が公表している車両故障データを見ても、エンジンオイルの品質がエンジントラブルの発生率に影響することが分かっています。
自動車整備振興会連合会の整備統計によると、エンジン関連の修理費用は年々増加傾向にあって、特に商用車では一度のエンジン修理で数十万円かかるケースも珍しくありません。そう考えると、予防のためのオイル代なんて安い投資だと思いませんか。
お客様への説明例:
「お客様の車両、ターボ車が多いですよね? SP規格はターボ車特有のトラブルを防ぐ性能があるので、エンジン保護がより確実なんです。もしエンジン修理となったら40〜50万円かかることもありますから、予防と考えれば全然高くないですよ」
メリット③ 燃費改善も期待できる
100%化学合成油は、鉱物油と比べて分子構造が均一で不純物が少ないため、エンジン内部の摩擦抵抗を減らす効果があります。
エンジンオイルの性能が燃費に影響することは業界関係者の間では広く知られており、国土交通省が推進する「エコドライブ」の取り組みでも、適切なオイル管理が燃費向上の要素の一つとされています。
化学合成油は理論上、燃費改善が期待できますが、実際の効果は車両の使用状況(走行パターン、積載重量、運転方法など)によって大きく変動します。そのため、燃費への影響を過度に期待するのではなく、まずは交換サイクルの延長やエンジン保護といった確実なメリットを主な目的として選択されることをおすすめします。
試算例(お客様への説明にそのまま使えます):
年間20,000km走行、実燃費8km/L、ガソリン代150円/Lの場合
- 年間燃料費:375,000円
- 仮に燃費が改善すれば、年間数千円〜1万円程度のコスト削減が期待できる可能性があります
- 車両10台なら、さらに効果が積み重なります
この数字、提案時の参考にしてください。お客様の車両台数と年間走行距離を聞けば、その場で試算できます。
法人顧客への具体的な提案の流れ
実際の商談で、どう切り出して、どう説明すればいいか。基本的な流れを紹介します。
ステップ1:現状のヒアリング
「今どんなオイル使ってます? ...SNの半合成ですか。なるほど。ちなみに年間どのくらい走りますか? ...1台2万キロ? けっこう走りますね。車は全部で何台?」
ステップ2:現状コストの見える化
「じゃあちょっと計算してみましょうか。今のSNグレードだと、5,000kmごとに交換が推奨されるので年4回ですよね。オイル代と工賃で1台あたり年間1万6千円くらい。5台だと年間8万円かかってる計算です」
ステップ3:化学合成油のメリット提示
「ここでSPグレードの化学合成油に変えると、10,000kmごとの交換で済むんです。年2回ですね。オイル代は上がりますけど、年2回だから1台あたり年1万円くらい。5台で年間5万2千円。つまり、年間で2万8千円くらい安くなるんですよ」
ステップ4:燃費改善と予防効果を追加
「それと、化学合成油だと燃費も改善する可能性があるんです。効果は使用状況によって変わりますが、少しでも改善すれば燃料費の削減にもつながります。
何より、SP規格は最新の規格なんで、特にターボ車のエンジン保護性能が高い。万が一エンジントラブルが起きたら修理で数十万円かかりますから、その予防と考えれば安い保険ですよね」
ステップ5:小さく始める提案でクロージング
「まず1台だけ試してみませんか? 3ヶ月使ってみて、効果を感じられなければ元に戻しても構いません。正直な話、ほとんどのお客さんが『調子いいね』って言って全台切り替えてますけどね」

えびすツールが整備工場の「3つの悩み」を解決する理由
ここまで提案方法を説明してきましたが、「どこから仕入れるか」も同じくらい重要です。えびすツールが整備工場から選ばれているのには、工場の悩みを解決できる明確な理由があります。
悩み1「利益が出ない」→ 解決策:事業者価格で仕入れられる
えびすツールは事業者専用のECサイトで、業務使用を前提とした卸売価格で提供しています。カー用品店の小売向け高級オイルと比べると、同等以上の性能でリットル単価が2〜3割くらい安いですね。
だから、販売価格を抑えながらも十分な利益を確保できます。「高性能だけど高すぎて提案できない」という悩み、これで解決できます。
悩み2「お客様に提案しにくい」→ 解決策:コスト削減の根拠データが揃っている
この記事で紹介した数値データをそのまま使えるので、「高いオイルを売りつけている」と思われず、論理的に提案できます。
交換サイクル延長による年間コスト削減額、燃費改善の可能性、エンジントラブル予防のメリット。これらの具体的な説明ができれば、お客様も納得しやすくなります。
悩み3「欠品でお客様を待たせる」→ 解決策:安定供給体制
法人のお客様から「いつものオイルで」って言われたときに、「今、欠品してまして...」じゃ信頼を失いますよね。
えびすツールは業務用途に特化した在庫管理と供給体制を整えてるので、必要なときに必要な量を確実に仕入れられます。これは整備工場にとって非常に重要なポイントです。
その他の特徴
請求書払い・掛け払いに対応
資金繰りに合わせた仕入れができます。クレジットカードだけじゃなくて、事業者にとって使いやすい支払い方法が選べるのは助かります。※掛け払いは審査が必要です
小ロットから大容量まで柔軟に対応
「まず試してみたい」という工場には4リットルサイズから、「まとめ買いでコストを下げたい」という工場には20リットルペール缶まで、使用量に応じて選べます。
えびすツールと他の仕入れ先との比較
| 項目 | えびすツール | カー用品店 | 一般的な卸業者 |
|---|---|---|---|
| 価格 | ◎ 事業者価格 | △ 小売価格 | ○ 卸価格 |
| 在庫安定性 | ◎ 業務用特化 | △ 品切れあり | ○ 普通 |
| 支払方法 | ◎ 掛け払い可 | △ 現金/カード | ○ 要相談 |
| サポート | ◎ 実務的相談可 | × なし | △ 限定的 |
| 小ロット対応 | ◎ 1本から | ◎ 可能 | △ まとめ買い前提 |
商品の詳細や価格は、えびすツールのエンジンオイルページで確認できます。
今日からできる3つのこと
この記事を読んで「なるほどね」で終わらせたら、何も変わりません。今日から始められることがあります。
1. まず1本、自分の車で試してみる
提案する前に、自分で体験しましょう。「実は自分も使ってるんですよ。明らかに違いますから」この一言が言えるかどうかで、提案の説得力が全然変わってきます。
2. この記事の数字を使って簡単な試算シートを作る
ExcelかGoogleスプレッドシートで、年間走行距離と車両台数を入力すれば自動でコスト比較ができるシートを作っておきましょう。タブレットやスマホで見せながら説明できるので、説得力が段違いです。
3. 次に来る法人客に提案してみる
「今日オイル交換ですよね。実は最近、業務車両のお客様に評判がいいオイルがありまして。年間のコストが下がる話なんですけど、ちょっとだけ時間いいですか?」この一言から始めてみてください。
提案しないことが最大のリスク
安いオイルを入れて、後でトラブル。高性能オイルを提案せずに、お客様が他の工場で知って、「なぜ教えてくれなかったの?」
提案しないことで失う信頼は、計り知れません。
逆に、お客様のコスト削減に貢献できれば、「あの工場は本当にこっちのことを考えてくれる」という信頼が生まれます。その信頼が、長期的な取引と、紹介による新規顧客につながっていきます。
えびすツールのSPグレード100%化学合成油は、あなたの提案を後押しする武器です。お客様のコスト削減に貢献できて、工場の信頼を高められて、売上アップにもつながる。何より、クレームのリスクを減らせる。
まずは1本、自分で試してみてください。その体験が、明日からの提案を変えます。