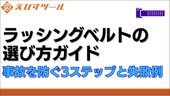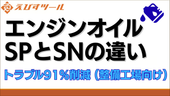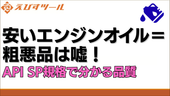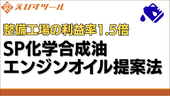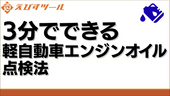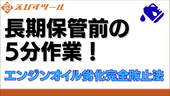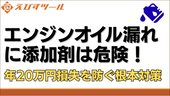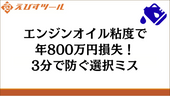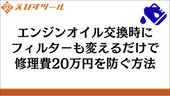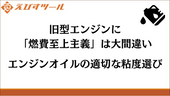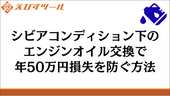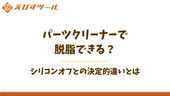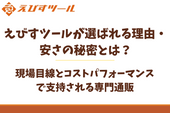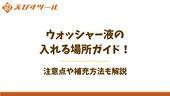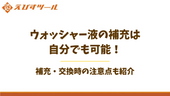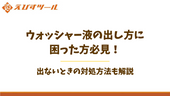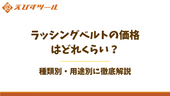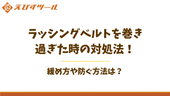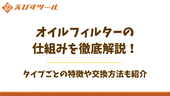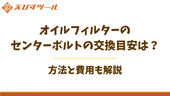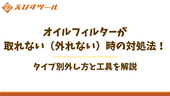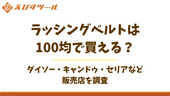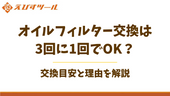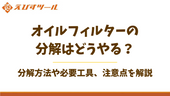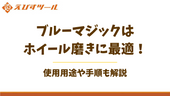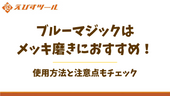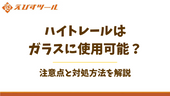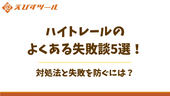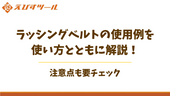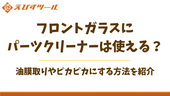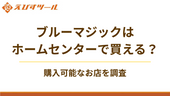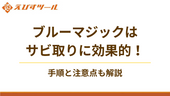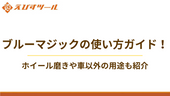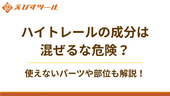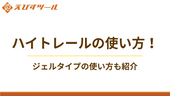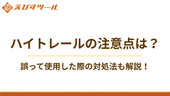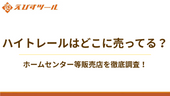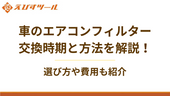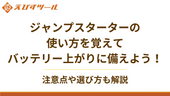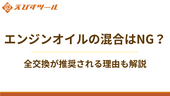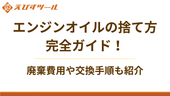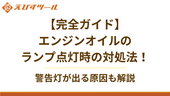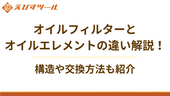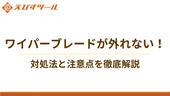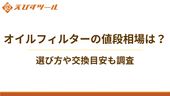ハイブリッド車の稼働時間管理は整備工場の新常識になる
「プリウスなんて、そんなに走ってないし、オイル交換なんてまだまだ先で大丈夫でしょ?」——最近、お客さまからこんな相談をよく受けませんか?ところが実際にエンジンを開けてみると、走行距離の割に内部にスラッジがべっとりと溜まっていて、「これはまずいぞ」と冷や汗をかいた経験がある方も多いはずです。
実は、ハイブリッド車は私たちが思っている以上に特殊な条件でエンジンが動いています。一般的なエンジンのみで走る車と比べて、エンジンの始動・停止回数が圧倒的に多く、しかもエンジンオイルの温度が上がりにくい特性があります。だからこそ、従来の「5,000km走ったらオイル交換」という常識では、とんでもない落とし穴にはまってしまうのです。

短時間稼働が生む隠れたリスク
ハイブリッド車の最大の特徴は、エンジンのオン・オフを繰り返すため稼働時間が短いことです。これは燃費向上には素晴らしいメリットですが、エンジンオイルにとっては厳しい環境を作り出しています。
オイルの温度が上がらないと、潤滑や防錆など、オイルの性能が発揮されません。さらに深刻なのは水分と燃料の混入問題です。エンジンの温度が上がりづらいと燃料が蒸発せず、オイルに燃料が混入して希釈・劣化が進みます。オートバックスも「頻繁にエンジンを始動停止させていると、燃料希釈が発生する可能性があります」と警告しており、これは業界共通の認識となっています。
さらに恐ろしいのは、走行距離が少なくても、空気中に含まれる水分がエンジンオイルに混入するため、劣化を促進してしまいます。つまり、「あまり走ってないから大丈夫」という常識は、ハイブリッド車では全く通用しないのです。
この劣化メカニズムが放置されると、エンジン内部スラッジによる始動不良、最悪の場合はエンジン焼き付きまで起こりえます。
エンジン修理費用は新品エンジンで100万円以上、中古やリビルトエンジンでも数十万円と高額になりますが、適切なオイル管理なら年間2~3万円程度。この差は実に10倍以上です。
稼働時間重視の管理システム導入
この問題を根本的に解決するには、従来の距離基準から「エンジン稼働時間」を重視した管理への転換が不可欠です。ハイブリッド車は、エンジンとモーターを併用して走行する構造を持ちますが、走行距離とエンジンの動作時間が比例関係にあることは間違いありません。
特に注意が必要なのは短距離走行が多いお客さまです。近所の買い物やちょっとした用事での使用が中心だと、エンジンが温まる前に停止してしまうことがほとんど。これでは、いくら走行距離が少なくても、オイルは確実に劣化していきます。
オートバックスやイエローハットなどの大手チェーンは、ハイブリッド車についても6ヶ月または5,000kmでの交換を推奨していますが、使用環境によってはさらに短い間隔が適切な場合も多いのが実情です。
特にシビアコンディション(渋滞が多い、短距離走行が中心など)では、3~4ヶ月での交換も視野に入れる必要があります。

ハイブリッド車専用0W-16オイルの選択が顧客満足の鍵
ハイブリッド車のメンテナンスで最も重要なのは、専用設計のエンジンオイルを選ぶことです。なぜかというと、ハイブリッド車特有の「ドライスタート」(エンジンの温度が上がらない状態でエンジンを掛けること)に対応できる性能が求められるからです。
ハイブリッド車には「0W-20」や「0W-16」などの、低粘度オイルが推奨されています。これらは単に燃費向上だけでなく、エンジンの始動時から各部にオイルが素早く行き渡るという重要な役割があります。エンジンの回転抵抗を減らしてくれるため、頻繁な始動・停止でもエンジンへの負担を最小限に抑えられます。
イエローハットはハイブリッド車用のエンジンオイルを販売しており、低温流動性・酸化安定性・省燃費性能に優れたSNグレード以降の規格を満たし、従来オイルでは対応しきれない厳しい条件でも確実にエンジンを保護するとのことです。交換費用は一般的なオイルより若干高めの5,000~6,000円程度(イエローハットの価格参考)ですが、エンジントラブルのリスクを考えると十分にペイする投資と言えるでしょう。
想定事例:先進的な取り組みによる差別化
【このようなケースが想定されます】
状況: 関東圏の中堅整備工場を想定します。ハイブリッド車の入庫台数が全体の3~4割程度を占めるようになったことを受けて、従来の距離ベース管理から稼働時間を考慮したメンテナンス提案への転換を検討。
損失リスク: 従来方式を継続した場合、短距離走行が多いハイブリッド車顧客からのエンジントラブル相談が年間3~5件程度発生し、うち1~2件で重大な修理(修理費用20万円~100万円)が必要になる可能性が考えられます。レッカー手配費用(1万円~2万円)、代車提供費用(1日5,000円×数週間)、長期修理による顧客満足度低下など、直接的な修理費用以上の損失が懸念されます。
改善施策: 全スタッフへのハイブリッド車特性教育の実施、顧客への説明資料整備が考えられます。短距離走行が多い顧客には3~4ヶ月での交換を積極提案し、ハイブリッド車専用0W-16オイル(交換費用5,000円~6,000円)の使用標準化、オイル交換履歴のデジタル管理、次回交換時期の事前通知システム構築などが実現可能な施策でしょう。
成果と対比: エンジントラブルによる重大修理の大幅削減を期待。顧客からも「エンジンの始動が静かになった」「燃費が良くなった」といった好評価につながり、リピート率向上、オイル交換頻度増加による売上増も見込まれる。
費用対効果: ハイブリッド車専用オイルの仕入れコスト増(1台あたり年間2,000円~3,000円)に対し、追加のオイル交換売上(1台あたり年間1万円~1.5万円増)と重大修理回避(年間50万円~200万円の損失回避)により、高い投資効果が期待できます。
(参考:修理費用20万円~100万円×年間数件×50台程度での試算。修理費用相場はオートバックス、イエローハット等より。ROI効果については大幅向上の業界データ等を参考に、中堅規模整備工場における投資回収効果を試算)
稼働時間管理による他の整備工場との差別化
今回ご紹介した稼働時間管理は、ハイブリッド車の普及が進む中で、整備工場にとって避けて通れない重要課題です。従来の距離基準だけでは予防できないトラブルを未然に防ぎ、お客さまの信頼獲得と収益性向上を同時に実現できる有効な差別化戦略と言えるでしょう。
特に、短距離走行が多い住宅地や高齢化が進む地域の整備工場では、従来のメンテナンススケジュールでは対応しきれないケースが今後さらに増加すると予想されます。ハイブリッド車専用オイルの適切な選択と稼働時間を意識した提案により、競合他社に先駆けて「ハイブリッド車に詳しい整備工場」としてのポジションを確立できるはずです。
また、このような専門性の高いサービスは価格競争に巻き込まれにくく、むしろ付加価値として適正な利益率を確保しやすいというメリットもあります。
今すぐ始められる稼働時間管理システムの構築
ハイブリッド車の適切なメンテナンス管理を始めるなら、まずはお客さまの使用パターン把握から始めてみてください。走行距離だけでなく、エンジンの始動回数や短距離走行の頻度を確認し、それに応じたオイル交換スケジュールを提案する体制を整えることが成功の第一歩です。
業界の変化に対応し、お客さまに最適なサービスを提供するために、ぜひ稼働時間管理という新しいアプローチを検討してみてください。