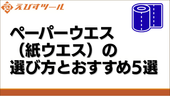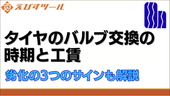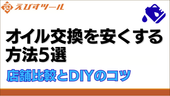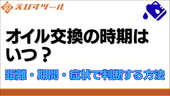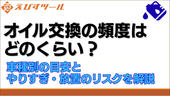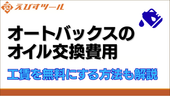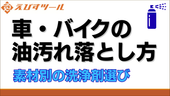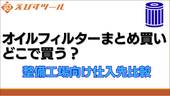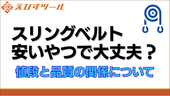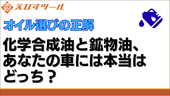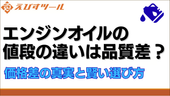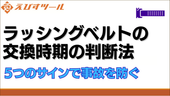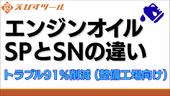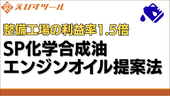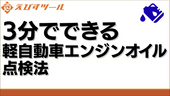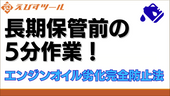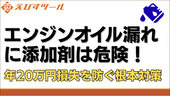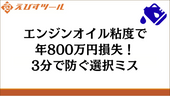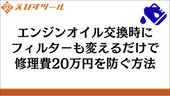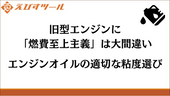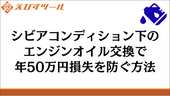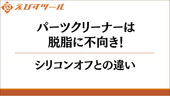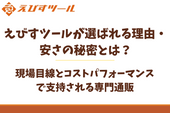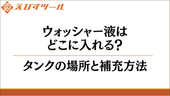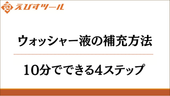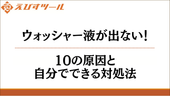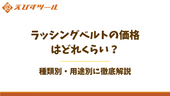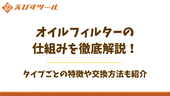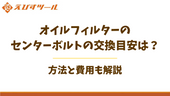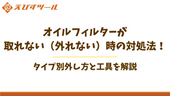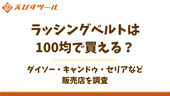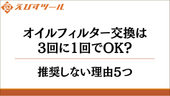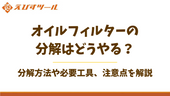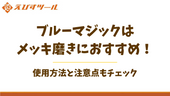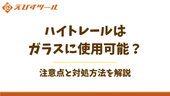「社長、またオイル値上げですか...」
仕入れ担当の整備士から、ため息混じりの報告を受けた経験はありませんか? 大手ブランドのオイルは年々値上がりし、利益率を圧迫する一方で、「安いオイルに変えたら、お客さんにクレーム言われるんじゃ...」という不安から、なかなか切り替えに踏み切れない。
この不安、よく分かります。実際、価格を理由にオイルを変えて、後から「エンジンの調子が悪い」と言われたらどうしますか? 修理費用を負担するのか、それとも説明不足を謝るのか。どちらにせよ、信用を失うリスクがあります。
だからといって、大手ブランドの高いオイルを使い続ければ、利益率はどんどん下がる。人件費も上がり、設備投資もしたい。でもオイル代が足を引っ張る—この悪循環、いつまで続けますか?
今回は、化学合成油の品質と価格の関係について、業界基準やスペック比較をもとに検証し、整備工場が自信を持ってオイルを選べる判断基準をお伝えします。
なぜ多くの整備工場が「高いオイル=安心」と思い込んでいるのか
実は、これには理由があります。
かつて(10年以上前)は、安価なエンジンオイルの中に品質の不安定な製品が混ざっていた時代がありました。規格表示が曖昧で、「安かろう悪かろう」が実際に存在したケースもあったのです。
しかし、2020年のAPI SP規格施行以降、状況は一変しました。規格認証の審査が厳格化され、認証を取得していない製品は事実上、市場での信頼を得にくくなったのです。
つまり、「安い=品質が不安」という常識は、もはや過去のものです。問題は、この事実を知らない整備工場が多いということ。規格認証という客観的な基準を知れば、品質を落とさずコストを大幅削減できる方法があるのです。
安価でも規格認証があれば高品質。鍵はAPI SP規格
エンジンオイルの品質を語る上で最も重要なのは、API(米国石油協会)規格やILSAC(国際潤滑油標準化承認委員会)規格といった国際基準への適合です。これらの規格は、エンジン保護性能、燃費性能、酸化安定性、低温流動性など、さまざまな項目で厳格な試験をクリアした製品にのみ与えられます。
API規格は世界中で広く認知されており、特にSP規格は2020年に導入された最新規格として、LSPI(低速早期点火)対策やターボチャージャー搭載エンジンへの対応が強化されています。
つまり、価格が安くても規格認証を満たしていれば、エンジン保護に必要な性能は保証されているということです。価格差の多くは、ブランド力や広告宣伝費、流通コストによるもので、オイル本来の性能差とは必ずしも一致しません。
整備現場で「安いオイルはすぐダメになる」という声を聞くことがありますが、実は規格外の製品や、使用環境に合わないオイルを選んだ結果である場合がほとんどです。適切な規格品を選べば、価格帯による性能差はほぼないというのが実情なんです。
これは、お客様への説明責任を果たす上でも重要なポイントになります。「API SP規格に適合しているので、大手ブランドと同等の性能です」と明確に伝えられれば、価格面での不安を払拭できますし、整備工場としての信頼獲得にもつながります。
API SP規格適合なら安価でも高品質。大手との性能差はほぼない
では、具体的にどの規格を基準にすればよいのでしょうか。現在、ガソリンエンジン用オイルで最も信頼性が高いのがAPI SP規格です。
API SP規格は、従来のSN規格と比較してLSPI(低速早期着火)対策やタイミングチェーンの摩耗低減性能が大幅に向上しています。LSPIは、ダウンサイジングターボエンジンで発生しやすい異常燃焼で、エンジンに深刻なダメージを与える可能性があります。最近の車に多いターボ車では、特に重要な対策項目です。
この規格に適合している製品であれば、メーカーや価格帯を問わず、一定水準以上の品質が保証されているわけです。大手ブランドの高価格帯オイルも、新興ブランドの低価格帯オイルも、SP規格をクリアしている限り、基本性能に大きな差はありません。
API規格は、米国石油協会から正式な認証を得ている製品には認証マーク(ドーナツマーク)が表示されており、このマークの有無が品質保証の判断基準となります。
整備工場にとって、この事実は経営上大きな意味を持ちます。規格適合品であれば、仕入れコストを抑えながら、お客様に高品質なサービスを提供できるからです。
大手ブランドとえびすツールのスペック比較
ここで、実際の製品スペックを比較してみましょう。以下は、大手ブランドの化学合成油と、えびすツールが提供するSPグレード100%化学合成油の主要スペックです。
比較表
| 項目 | 大手ブランドA | えびすツール SPグレード |
|---|---|---|
| API規格 | SP | SP |
| 粘度グレード | 5W-30 | 5W-30 |
| ベースオイル | 100%化学合成 | 100%化学合成 |
| LSPI対策 | ○ | ○ |
| 酸化安定性 | 高 | 高 |
| 低温流動性 | -35℃以下 | -35℃以下 |
| 参考価格(4L) | 約6,000〜8,000円 | 2,400円 |
規格・性能面ではほぼ同等の仕様を持ちながら、価格は半額以下に抑えられています。
特に注目すべきは、どちらもAPI SP規格に適合し、LSPI対策が施されている点です。これは最新のダウンサイジングターボエンジンにも安心して使用できることを意味します。
また、化学合成油の特徴である高い酸化安定性や優れた低温始動性も、両製品とも同水準で確保されています。つまり、エンジン保護性能や使用寿命において、実用上の差はほとんないということです。
価格差の要因は、主に流通構造とブランディングコストにあります。大手メーカーは全国規模の広告展開や多段階の流通網を持つため、製品価格にそのコストが上乗せされます。一方、えびすツールのような直販メーカーは、中間マージンを削減し、必要な品質を確保しながら低価格を実現しているのです。
整備工場が安価な化学合成油を選ぶメリット
規格認証済みの安価な化学合成油を採用することで、整備工場はどんなメリットを得られるのでしょうか。想定されるケースをもとに見ていきましょう。
コスト削減で年間150万円以上の差
想定ケース: 月間50回のオイル交換を行う整備工場の場合
- 現行品(大手ブランド): 6,000円×50本×12ヶ月=360万円
- えびすツール: 3,500円×50本×12ヶ月=210万円
- 年間削減額: 150万円
※上記は4L缶での試算例です。実際の削減額は、仕入れ価格や使用量によって異なります。
この差額を、リフトやタイヤチェンジャーなどの設備投資に回せば、作業効率が上がります。整備士の資格取得支援に使えば、技術力の底上げにもなります。あるいは、人材採用の原資にすることもできます。
また、オイル交換の利益率を維持したまま、お客様への請求額を抑えることも可能です。「他店より安いのに、品質は同じ」という訴求は、価格競争力を高め、新規顧客の獲得やリピート率向上が期待できます。
お客様の「このオイル大丈夫?」に自信を持って答えられる
「品質を落とさず工賃を抑える」というバランスは、お客様にとって最も魅力的な提案です。API SP規格という客観的な品質保証があるため、「なぜこの価格で提供できるのか」を論理的に説明でき、お客様の不安を解消できます。
想定される会話例としては、「このオイル、聞いたことないメーカーだけど大丈夫?」という質問に対して、「API SP規格に正式適合しているので、大手ブランドと同等の性能です」と自信を持って答えられることが、整備士としての専門性をアピールし、お客様からの信頼度を高めます。
規格の話をすると、多くの場合は納得していただけるでしょう。説明の仕方一つで、お客様の受け止め方は大きく変わります。
在庫管理が楽になり、発注のストレスも軽減
高品質な化学合成油であれば、複数の粘度グレードに対応できるため、在庫品目を絞り込めます。例えば、5W-30と0W-20の2種類で大半の車種をカバーできれば、在庫スペースの削減や発注業務の簡素化が可能です。(あいにく、えびすツールで販売しているエンジンオイルは5W-30のみです)
また、酸化安定性の高い化学合成油は長期保管にも適しているため、まとめ買いによるコスト削減も実現しやすくなります。「月末に在庫が足りない!」という慌ただしさからも解放されるでしょう。
在庫を絞り込めば、棚卸しも早く終わりますし、何より「あれ、どこに置いたっけ?」と探す時間が減ります。地味ですが、日々の業務効率は確実に上がるはずです。
リピーターが増え、経営の安定性が高まる
次回交換時に「前回と同じ高品質オイルで、お得な価格です」と提案できれば、お客様は安心して継続利用を決断します。価格と品質のバランスが良い整備工場は、お客様にとって「通い続けたい店」になります。
リピーターが増えれば、新規集客にかかるコストも抑えられます。結果的に、経営の安定性が高まるわけです。
整備工場がオイルを選ぶ際の3ステップ判断法
では、実際にどのようにオイルを選べばよいのでしょうか。以下の3ステップで判断すれば、失敗のない選択が可能です。
ステップ1: 規格表記の確認
まず、製品パッケージや商品ページにAPI SP規格またはILSAC GF-6規格の表記があるかを確認してください。API規格の正式認証を受けている製品には、APIシンボルマーク(ドーナツマーク)が表示されており、これが品質保証の最も確実な指標です。
規格表記がない製品や、聞き慣れない独自規格のみを謳う製品は避けるべきです。国際的に認められた基準こそが、お客様への説明責任を果たす根拠となります。
ステップ2: 取扱車種との適合確認
次に、自社で扱う主要車種の推奨粘度をリストアップし、それらをカバーできる粘度グレードを選びます。最近の燃費性能に優れた車では、取扱説明書で指定されているエンジンオイルを使用しないと、車本来の性能を発揮できません。
多くの国産車は5W-30または0W-20を推奨しているため、この2種類を揃えれば大半の需要に対応できます。輸入車や特殊車両が多い場合は、5W-40や10W-40なども検討しましょう。ただし、在庫品目を増やしすぎると管理コストが上がるため、売れ筋を見極めることが重要です。
ステップ3: 仕入れコストの試算
最後に、月間のオイル使用量と単価から、年間の仕入れコストを試算します。現在使用しているオイルとの価格差を計算し、年間でどれだけ削減できるかを明確にしましょう。
削減額が見えてくると、「この分を何に使おうか」と前向きに考えられるようになります。設備投資か、人材育成か、あるいは広告宣伝か。選択肢が広がるのは嬉しいものです。
えびすツールのSPグレード化学合成油が選ばれる理由
えびすツールのエンジンオイルは2025年1月から販売を開始していますが、多くの整備工場などから支持されています。その理由は以下の通りです。
規格認証に基づく確かな品質
えびすツールのSPグレード100%化学合成油は、API SP規格に正式に適合しています。これは国際基準をクリアした証であり、エンジン保護性能が公的に保証されていることを意味します。
規格認証を取得している製品であれば、品質面での心配は不要です。多くの運送会社や整備工場が、コスト削減とメンテナンス品質の両立を目的にえびすツールのオイルを採用しています。
100%化学合成油ならではの高性能
化学合成油は、鉱物油と比べて分子構造が均一です。そのため、以下のような優れた特性を持ちます。
- 高温でもサラサラ感が続く。真夏の渋滞でも粘度が安定
- 冬場の始動がスムーズ。エンジンへの負担を最小限に
- 劣化しにくいから、交換サイクルを延ばせる
- 結果的に燃費も良くなる
えびすツールのエンジンオイルは、100%化学合成油であるため、部分合成油や鉱物油よりも長期間にわたって性能を維持できます。
直販体制による圧倒的なコストパフォーマンス
えびすツールは、製品の直販体制を敷いているため、中間マージンを削減し、高品質なオイルをリーズナブルな価格で提供できます。整備工場にとって、品質を維持しながらコストを削減できることは、経営上の大きなメリットです。
安心のサポート体制
購入後のサポートも充実しており、不明点がありましたら、専門スタッフが丁寧に対応します。初めて採用する整備工場でも、安心して切り替えられる体制が整っています。
オイルコストを削減した整備工場に起きること
実際にオイルを切り替えた場合、どのような変化が起きるでしょうか。想定されるケースを見ていきましょう。
変化1: 価格競争力が上がり、新規客獲得の可能性が高まる
「うちは品質を落とさず、価格を抑えています」と言えるようになれば、価格重視のお客様も安心して来店しやすくなります。地域での口コミや紹介が増える可能性もあります。
変化2: 利益率が改善し、設備投資の選択肢が広がる
年間150万円のコスト削減は、新しいリフト1台分に相当します。作業効率が上がれば、さらに売上も伸びる可能性があります。あるいは、診断機器の導入や工場の環境改善にも使えます。
変化3: 整備士のストレス軽減と働きやすさの向上
「なぜこんなに高いオイルを使わないといけないんだ」というストレスから解放され、合理的な仕入れができるようになります。無駄なコストを削減できたという達成感は、職場の雰囲気を良くすることにもつながるでしょう。
オイル一つで、これだけの変化が起きる可能性があるのです。
明日からできる、失敗しないオイル切り替えの手順
もし、えびすツールのオイルを試してみたいなら、以下の手順で進めれば、リスクを最小限にできます。
ステップ1: 少量(1〜2本)を試験的に導入
→ まずは自社の車、または協力的なお客様の車で試す
ステップ2: 次回点検時に状態を確認
→ エンジン音、オイルの劣化具合をチェック
ステップ3: 問題なければ本格導入を検討
→ コスト削減効果を実感しながら、徐々に切り替え
いきなり全てを切り替える必要はありません。小さく始めて、確信を持ってから広げる。これが賢いやり方です。
今すぐオイル仕入れを見直しませんか
エンジンオイルの見直しは、設備投資不要で即効性のあるコスト削減策です。月間のオイル使用量を把握して、年間削減額をシミュレーションしてみてください。
「品質は譲れないが、コストは抑えたい」—これは、すべての整備工場経営者が抱える共通の課題です。しかし、規格認証という「正しい判断基準」を知れば、この課題は意外と簡単に解決できます。
API SP規格に適合した化学合成油であれば、大手ブランドと同等の性能を持ちながら、大幅なコスト削減が実現可能です。そして、その削減した経費を、お客様へのサービス向上や事業拡大に投資することで、整備工場全体の競争力が高まります。
えびすツールのSPグレード100%化学合成油は、規格認証済みの高品質を適正価格で提供することで、整備工場の経営課題を解決します。
正直、最初は「本当に大丈夫か?」と思うかもしれません。でも、規格を見れば納得できるはずです。まずは商品ページで、スペックだけでも確認してみてください。