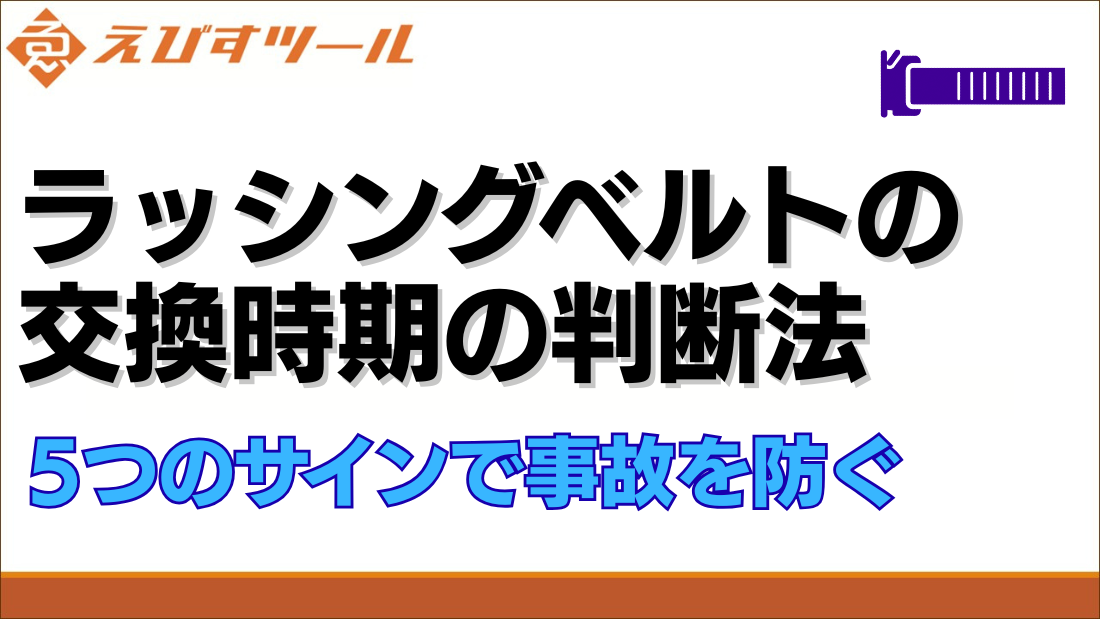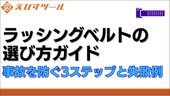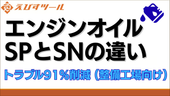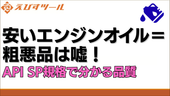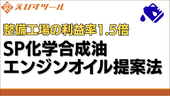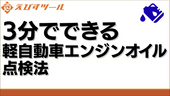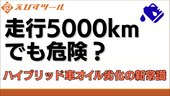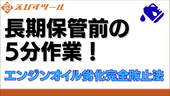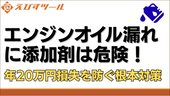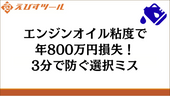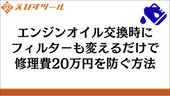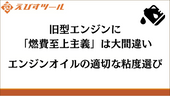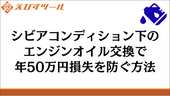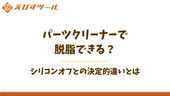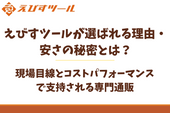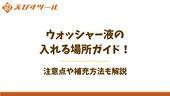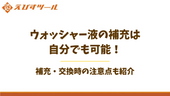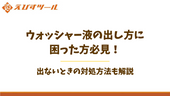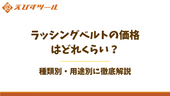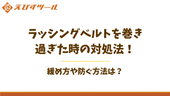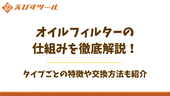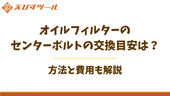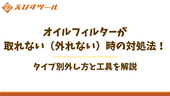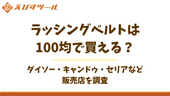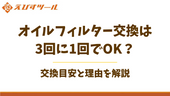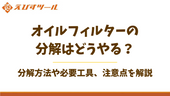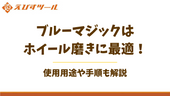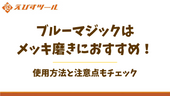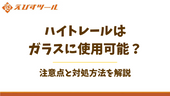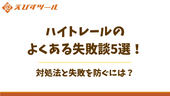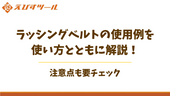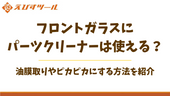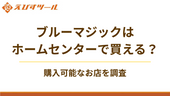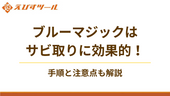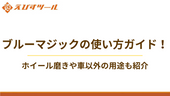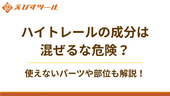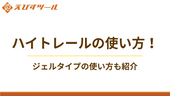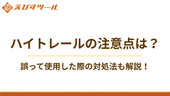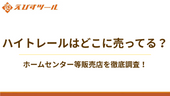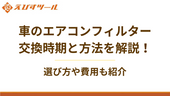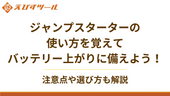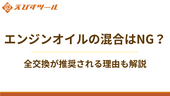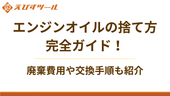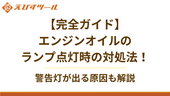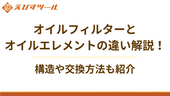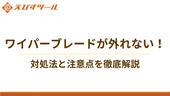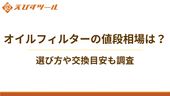「ラッシングベルトの交換時期がわからない」
「いつまで使えるのか寿命の判断基準を知りたい」
運送会社の経営者や購買担当の方から、こうした相談をよくいただきます。ドライバーからは「まだ大丈夫ですよ」と言われるものの、本当に安全なのか判断に迷う。ラッシングベルトの交換時期の見極めは、安全性とコストのバランスを取る、なかなか難しい判断です。
適切な交換サイクルを守ることで、事故リスクを大幅に下げながら、無駄な交換コストも削減できます。今回は、現場ですぐに使える具体的な判断基準と、明日から始められる管理方法をご紹介します。
定期的な交換・点検が事故防止とコスト削減を両立させる
ラッシングベルトは消耗品です。これは誰もが理解していることですが、「いつ交換するか」の判断は本当に難しい。定期的な交換と点検を行うことで、荷崩れや破断による事故を未然に防ぎ、結果的にコストを削減できるとわかっていても、現場の判断は悩ましいものです。
「まだ使えそうだから」と劣化したベルトを使い続けると、走行中の荷崩れや重大事故につながるリスクがあります。想定される損失額を考えてみましょう。
荷物の損傷、配送遅延、車両修理、そして最悪の場合は人身事故。これらが発生した場合、会社が負担する金額は決して小さくありません。さらに見逃せないのが、会社の信用失墜による取引停止というリスクです。
一方で、ラッシングベルト1本の交換コストはどうでしょうか。一般的な製品では数千円程度です。この差を考えれば、適切なタイミングでの交換は「出費」ではなく「投資」といえます。
ただし、まだ十分に使えるベルトを早期に廃棄してしまうのも無駄なコスト。ここが悩みどころですね。適切な交換タイミングを見極めることで、安全性を確保しながら、無駄な出費も抑えることができます。
ラッシングベルトの寿命を縮める劣化の主な原因
そもそも、なぜラッシングベルトは交換が必要なのか。劣化のメカニズムを理解しておくと、点検時の判断精度が上がります。
摩耗による強度低下
使用のたびに荷物や荷台、フックとの摩擦で繊維が削れていきます。ポリエステル繊維は一本一本が荷重を支えているため、目に見えないレベルの摩耗でも破断強度は確実に低下します。特に角張った荷物や金属製の固定点と接する部分は要注意です。
現場でよく見られるのは、同じ場所ばかりが摩耗しているケース。荷台の特定の位置で固定することが多い場合、その部分だけが集中的に劣化していきます。
紫外線による材質の劣化
屋外での使用・保管により、紫外線が繊維の分子構造を変化させ、強度と柔軟性が失われます。色褪せや硬化は紫外線劣化の典型的なサインです。
鮮やかだった色が白っぽくなったり、触ったときに硬くゴワゴワしている場合は、かなり劣化が進行しています。特に夏場、直射日光の当たる場所に放置していたベルトは要注意です。
荷重オーバーによる内部ダメージ
最大使用荷重を超えた負荷で、繊維内部に微細な断裂が発生します。一度の過負荷では破損しなくても、ダメージは確実に蓄積していきます。
見た目は問題なくても、内部では確実に劣化が進んでいる可能性があります。これらの要因は単独ではなく、複合的に作用します。摩耗したベルトが紫外線にさらされ、さらに過負荷がかかれば、劣化スピードは想像以上に速くなります。

今すぐ交換すべきラッシングベルトのサイン
では、具体的にどのような状態になったら交換すべきなのか。以下のサインが一つでも見られたら、そのベルトはすぐに使用を中止してください。
表面の摩耗・毛羽立ち
ベルト表面を指でなぞってみてください。ザラつきや毛羽立ちを感じたら要注意です。特にベルトが荷物や荷台に接触する部分、フック近くの折り返し部分は入念にチェックが必要です。
部分的に細くなっている箇所や、繊維が切れてほつれている場合は、即座に交換してください。その部分から破断する可能性が非常に高くなっています。
明らかな色褪せ・変色
購入時と比べて明らかに色が薄くなっている場合は、紫外線による劣化が進んでいます。判断に迷うときは、同時期に購入したベルトや屋内保管していたベルトと比較してみてください。明らかに色の差がある場合は交換のサインです。
屋外保管が多い現場では、定期的に色の変化をチェックすることをおすすめします。「少し色が薄くなってきたかな」と感じたら、そろそろ交換を検討する時期です。
生地の硬化・柔軟性の喪失
新品のときは柔らかくしなやかだったベルトが、硬くなってゴワゴワしているようなら劣化が進んでいます。折り曲げたときに違和感がある、以前より巻き取りにくいと感じたら要注意です。
硬化したベルトは衝撃吸収性も低下しているため、急ブレーキ時などに荷物にかかる衝撃を適切に受け止められません。また、荷物の形状にフィットせず固定力も低下します。
フック・金具の変形や損傷
ベルトだけでなく、フックや金具部分の状態も重要なチェックポイントです。フックが曲がっている、開き具合が変わっている、亀裂が入っている、表面に深い傷があるといった変形が見られる場合は、過負荷がかかった証拠です。
金具に異常が見られたら、ベルト本体に目に見える損傷がなくても、ベルト全体の交換を検討してください。金具の変形は、ベルト本体にも同様の負荷がかかっていることを意味しています。変形したフックは固定点から外れやすく、非常に危険です。
ラチェット機構の動作不良
ラチェット部分がスムーズに動かない、締め付けが甘い、以前より締めにくい、勝手に緩むといった症状がある場合は、内部機構の摩耗や破損が考えられます。
これらの不具合は走行中の緩みに直結し、荷崩れの原因となります。「少し締めにくいけど、まだ使える」という判断は避けてください。ラチェットの動作に少しでも違和感を感じたら、すぐに交換が必要です。

使用環境別の交換サイクル目安
ラッシングベルトの寿命は、使用環境や頻度によって大きく異なります。以下は一般的な目安ですが、前述のサインが見られたら、期間に関わらず即座に交換してください。
毎日使用する現場の場合
毎日荷物の積み降ろしを行う運送業の現場では、6ヶ月から1年を目安に交換を検討してください。使用頻度が高いほど摩耗も早く進みます。
現場での工夫として想定されるのは、複数本をローテーションで使用することです。これにより各ベルトの負担を分散し、寿命を延ばすことができます。
週に数回使用する現場の場合
週に数回程度の使用であれば、1年から1年半が交換の目安となります。ただし、屋外での保管が多い場合は紫外線の影響を受けやすいため、1年程度での点検を推奨します。使用後は必ず屋内で保管する、直射日光を避けるなどの工夫で、寿命を延ばすことができます。
月に数回使用する現場の場合
使用頻度が低い場合でも、2年から3年での交換を検討してください。「あまり使っていないから大丈夫」という思い込みは危険です。使わずに保管しているだけでも、紫外線や湿気、温度変化などで劣化は進行します。
長期間使用していないベルトほど、使用前の入念な点検が必要です。久しぶりに使うベルトは、必ず点検してから使用してください。

今日から始められる管理方法
交換時期を見極めるには、日常的な管理が欠かせません。といっても、難しい管理システムは不要です。以下の方法を実践するだけで、ベルトの状態を把握し、適切な交換サイクルを実現できます。
購入日をベルトに直接記入する
最もシンプルで効果的な方法です。ベルトを購入したら、ラチェット部分やベルトの端に、油性マジックで購入年月を記入しましょう。「2025.10」のように、年月を書くだけで十分です。
これだけで使用期間が一目でわかり、「そろそろ1年だな」「まだ3ヶ月だから問題ないだろう」といった判断が容易になります。複数のベルトを管理する現場では特に有効で、すぐに効果を実感できるはずです。
月に一度の一斉点検日を設定する
月初めの安全会議の日や、毎月1日など、決まった日に保有している全てのラッシングベルトを点検する習慣をつけましょう。
点検項目は前述のサイン(摩耗、色褪せ、硬化、金具変形、ラチェット不良)です。簡単なチェックリストを作成し、各ベルトの状態を記録しておくと、劣化の進行具合も把握できます。点検自体は10分から15分程度で完了し、これだけで重大事故を未然に防げます。
「使用禁止」ベルトの明確な分離
点検で異常が見つかったベルトは、その場で使用禁止にすることが重要です。「次の配送までは使える」という判断は絶対に避けてください。
現場に「要交換BOX」を用意し(段ボール箱やプラスチックケースでOK)、異常があるベルトはすぐにそこへ入れる運用にしましょう。赤いテープを貼るなど、視覚的に「使用禁止」とわかるようにするとより効果的です。
正直なところ、現場では「もったいない」「まだ使えるのに」という声が出ることもあります。しかし、一度の判断ミスが取り返しのつかない事故につながることを考えれば、迷わず使用中止にすべきです。
えびすツールのラッシングベルトで更新コストを抑える
定期的な交換が必要とはいえ、コストは抑えたいというのが現場の本音です。えびすツールのラッシングベルトなら、高品質でありながらコストパフォーマンスに優れており、計画的な交換管理を無理なく実現できます。
なぜ多くの運送会社がえびすツールを選んでいるのか
理由1:適正価格で交換コストを削減できる
品質を維持しながら適正価格で提供することで、定期的な交換を心理的・経済的ハードルなく実行できます。「高すぎて交換を先延ばししてしまう」という状況を防ぎ、適切なタイミングでの交換を実現します。
理由2:フック形状の選択肢が豊富
固定点の形状は現場によって様々です。えびすツールでは4種類のフック形状から選べるため、無理な固定による早期劣化を防げます。適切な形状を選ぶことで、ベルトの寿命を最大限に延ばすことができます。
理由3:在庫確保と迅速な配送体制
急な交換が必要になったとき、「在庫がない」「納期が遅い」では業務に支障が出てしまいます。えびすツールでは在庫を豊富に確保しており、急な交換が必要になった際も素早く対応可能です。
複数台のトラックを運用している事業者の方は、交換時期を考慮してまとめて購入することで、在庫管理の手間を減らせます。計画的な購入により、現場での欠品を防ぎ、常に十分な在庫を確保できます。
まとめ:あなたの現場は今すぐ交換が必要か?
ラッシングベルトの寿命管理は、特別な設備や複雑なシステムを必要としません。まず、あなたの現場の状況を確認しましょう。
今すぐ交換が必要な現場(該当したら即日対応)
- ベルトに摩耗・色褪せ・硬化・金具変形・ラチェット不良のいずれかがある
- 最後の交換から1年以上経過している(毎日使用の場合)
- 過去6ヶ月以内に過負荷をかけた可能性がある
- 購入時期が不明なベルトがある
【今日やること】
保有している全てのベルトを点検してください。
5つのサイン(摩耗、色褪せ、硬化、金具の変形、ラチェット不良)に照らしてチェックし、一つでも該当すれば使用を中止します。「次の配送までなら」という判断はせず、その場で使用禁止にしてください。
1ヶ月以内に点検・交換を検討すべき現場
- 最後の交換から6ヶ月以上経過している(毎日使用の場合)
- 屋外保管が多く、色の変化が気になり始めている
- 最近、ラチェットの締め付けが以前より硬いと感じる
【今週中にやること】
点検で見つかった問題のあるベルト、使用期間が長いベルトをリストアップしましょう。そしてえびすツールのラッシングベルトで最適な製品を選んでください。フック形状は現場の固定点に合わせて選択します。
現状維持でOKだが定期点検は必須
- 購入から3ヶ月以内で、5つのサインが一切ない
- 月1回の点検を既に実施している
- 使用頻度が低く、屋内保管を徹底している
【継続的にやること】
・購入日の記入
・月初の一斉点検
・要交換BOXの設置
この3つのルールを現場に導入し、習慣化しましょう。簡単な管理台帳(エクセルやノートで十分)を作成すれば、より計画的な交換が実現できます。
あなたの現場はどれに該当しますか?
該当する内容に応じて、今日からアクションを始めましょう。
使用頻度に応じた交換サイクルを目安にしながら、最終的にはベルトの状態で判断してください。期間はあくまで目安です。サインが出ていれば、期間に関わらず交換が必要です。
安全は何にも代えがたい財産です。ラッシングベルトの適切な管理で、事故ゼロの現場を実現しましょう。