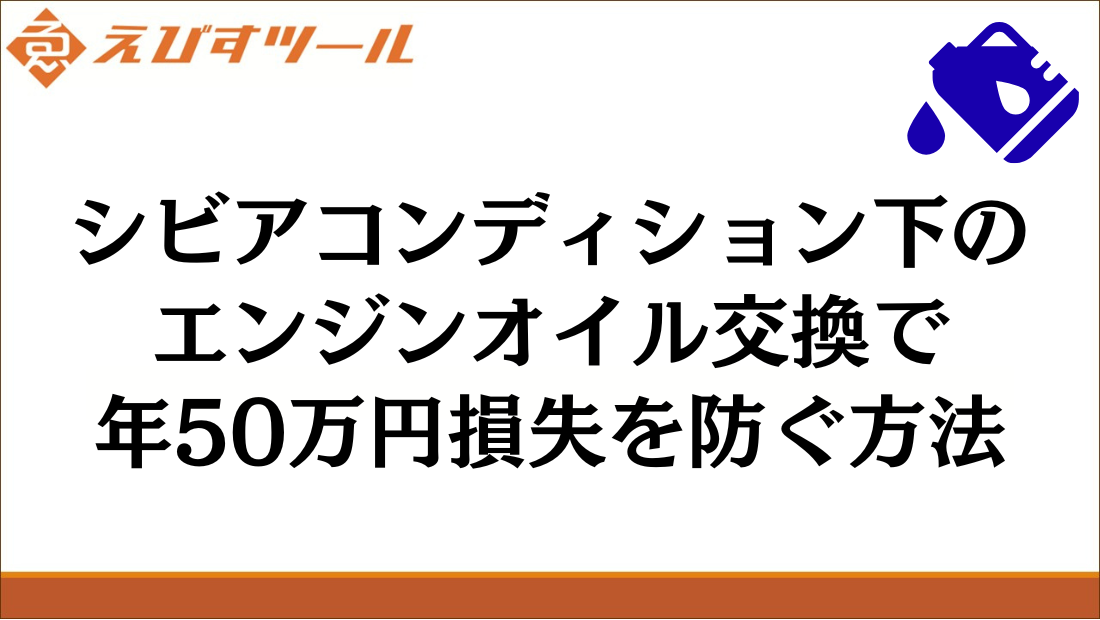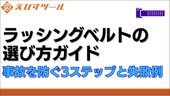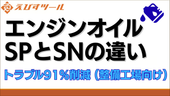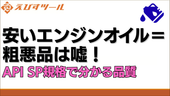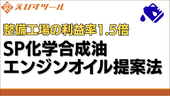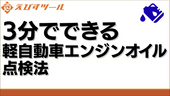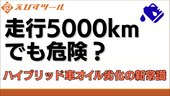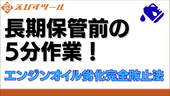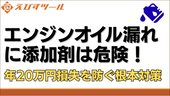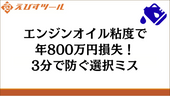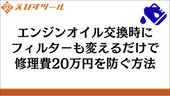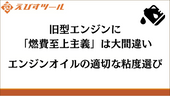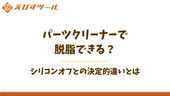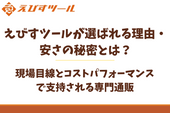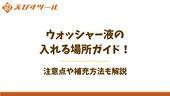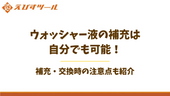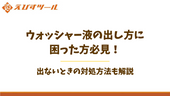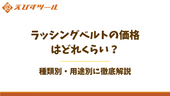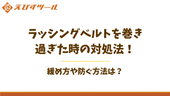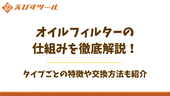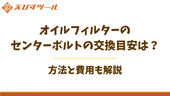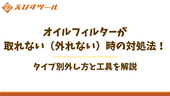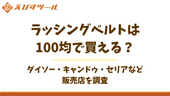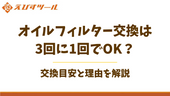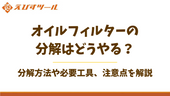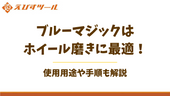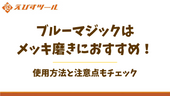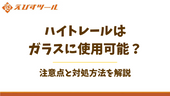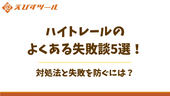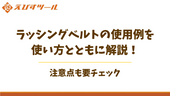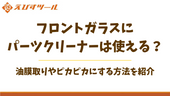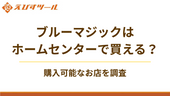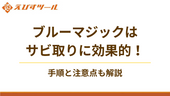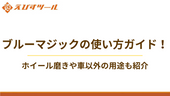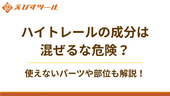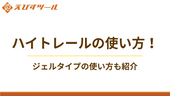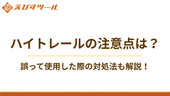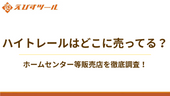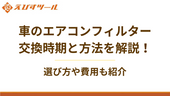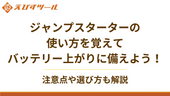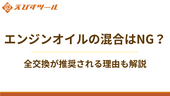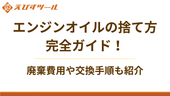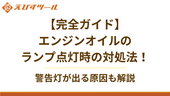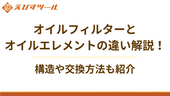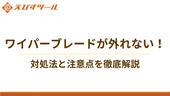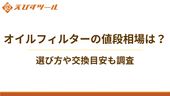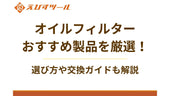「走行距離が少ないから大丈夫」という思い込みが引き起こす深刻な損失
「うちは短距離配送が中心だから、オイル交換は走行距離を見て判断すればいい」—そんな声をよく耳にします。
しかし、この常識こそが、年間数十万円から数百万円の修理費を生み出す根本原因だったのです。
実際、ホンダやトヨタなど主要メーカーは、1回あたり8km以内の短距離走行を明確に「シビアコンディション」と定義しており、標準的な使用環境よりもエンジンオイルの劣化が加速することを公式に警告しています。にも関わらず、現場では「距離が短いから負担も軽い」という誤解が蔓延しているのが実情です。
整備工場においては、お客様から「そんなに走ってないのに、なぜもうオイル交換が必要なのか」と質問された経験があるでしょう。その疑問にお答えするために、科学的根拠と想定される損失データを踏まえて解説していきます。

シビアコンディション下のオイル劣化が招く重大リスク
エンジンオイルの劣化メカニズムを正しく理解すると、なぜ短距離運行が「シビアコンディション」と呼ばれるのかが明確になります。
水分混入による乳化現象
短距離走行ではエンジンオイルの温度が上がりきらないため、大気中の水分が蒸発せずにエンジンオイルに取り込まれてしまいます。エンジン内部で発生する結露と相まって、オイルが白く濁る「乳化現象」が発生し、本来の潤滑性能を大幅に低下させます。
燃焼不完全による汚れの蓄積
エンジンが十分に温まらない状態での運転では、燃焼効率が95%から80~85%まで低下し、未燃燃料がオイルに混入。これにより、エンジン内部にマヨネーズ状の堆積物が形成され、オイル流路の閉塞を引き起こします。
エンジンオイル交換を怠った場合の修理費用は深刻です。エンジン本体が破損すると数十万円から最悪100万円を超える修理費用がかかることも珍しくありません。
特に、オイル劣化による焼付きが発生した場合、エンジンオーバーホールや載せ替えが必要となり、車両の稼働停止期間も含めた総損失は計り知れません。
適切なオイル交換周期が車両管理費を削減する
科学的根拠に基づいた適切なオイル交換こそが、車両管理費を削減する最も確実な方法です。
メーカー推奨基準の活用
トヨタはシビアコンディション下では7,500km毎または6ヶ月毎、ホンダも同様に7,500km毎または6ヶ月毎の交換を推奨しています。
これは単なる目安ではなく、自動車メーカーにおける長年の技術データに基づいた科学的根拠のある基準なのです。
実践的な管理フロー
効果的なオイル管理には、走行距離と期間の両面からのアプローチが不可欠です。特に短距離・渋滞中心の運行では、走行距離よりも期間を重視した6ヶ月周期での交換が重要になります。さらに、オイルの色や粘度の目視確認を併用することで、より精密な状態管理が可能になります。
車両ごとのメンテナンス記録を整備し、交換履歴を一元管理することで、予防整備の効果を数値で把握できるようになります。

高品質エンジンオイルの採用が良い選択
コスト削減を重視するあまり、安価なオイルを選択するケースがありますが、これは短期的な節約が長期的な大損失を招く典型例です。
オイル品質と耐久性の関係
高品質なエンジンオイルは、優れた清浄分散性能と耐熱性を備えており、シビアコンディション下でも安定した性能を維持します。添加剤の配合技術により、汚れの蓄積を抑制し、水分混入による乳化も防止できます。
特に、API規格やILSAC規格をクリアした高品質オイルは、温度変化に対する粘度安定性に優れており、エンジン保護効果が格段に向上します。
【SP GF-6A 全合成油】えびすツールの
エンジンオイルはこちら
選定時の重要ポイント
車両の使用環境と走行パターンに最適化されたオイル選択が重要です。短距離・渋滞運行が多い車両には、低温流動性と高温安定性のバランスに優れた全合成油が適しています。
また、オイルフィルターとの同時交換により、システム全体の清浄性を維持することで、オイル性能を最大限に活用できます。
【安価だけどISO9001】えびすツールの
オイルフィルターはこちら
予防整備を行わないことによる想定損害額
適切なオイル管理による予防整備の効果は、数値として明確に現れます。
【このようなケースが想定されます】
短距離配送を中心とした軽トラック5~10台程度を運用する中小運送会社を想定します。従来は走行距離のみを基準としたオイル交換により、年間約1万km走行する車両でも12ヶ月に1回程度の交換頻度の場合。
この運用では、エンジン不調による修理費が年間数十万円発生する可能性があり、重大な故障で数週間から1ヶ月以上の休車を余儀なくされるケースも想定されます。これにより、代替車両の手配費用と機会損失を含めて相当な追加コストが発生するでしょう。
予防整備計画の見直しにより、6ヶ月周期でのオイル交換と高品質オイルの採用を実施した場合を想定します。オイル交換費用は年間で増加しますが、エンジン関連の故障リスクが大幅に軽減され、燃費の改善も期待できます。
結果として、修理費の削減、代替車費用の削減、燃費改善による節約効果が見込まれ、追加投資に対して高い効果が期待できます。さらに車両の資産価値維持にも寄与する可能性があります。
(参考:修理費用の見積りは一般的な費用で試算。燃費改善効果については実測例で向上事例の業界データ等を参考に、小規模事業者における予防整備効果を試算)
まとめ
エンジンオイル管理は単なるメンテナンス作業ではなく、車両の総合的な資産価値を維持する経営戦略そのものです。
ホンダが公式に示しているように、シビアコンディション下では標準よりも早めの点検・交換が必要であり、この基準を遵守することで長期的な車両価値の最大化が可能になります。
特に、整備工場にとっては、お客様への適切な提案により信頼関係を構築し、継続的な来店につなげる重要な機会でもあります。科学的根拠を示しながら説明することで、お客様の理解と納得を得やすくなり、結果として双方にメリットのある関係を築けます。
効果的なエンジンオイル管理は今すぐ始められます
これからは、以下の行動を推奨します。
まず、現在管理している車両の使用パターンを詳しく分析し、シビアコンディションに該当する車両を特定してください。次に、それらの車両について6ヶ月周期での予防交換計画を策定し、高品質オイルへの切り替えを検討してください。
整備記録の電子化により、車両ごとの履歴管理を行い、効果測定を継続することで、さらなる改善点を見つけることができるでしょう。
この記事で紹介した科学的根拠と実践方法を活用すれば、エンジントラブルによる突発的な損失を未然に防ぎ、車両運用コストを大幅に削減することが可能になります。。