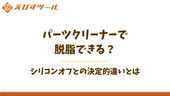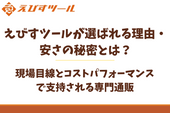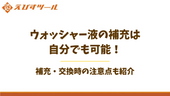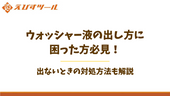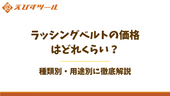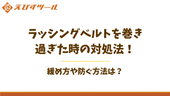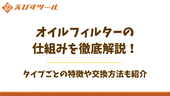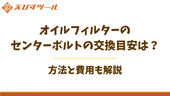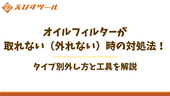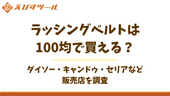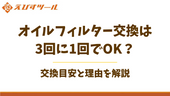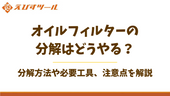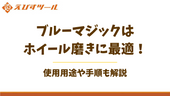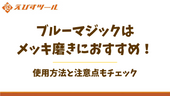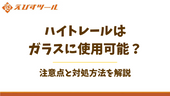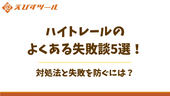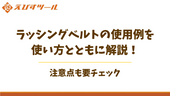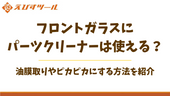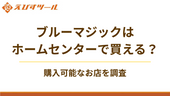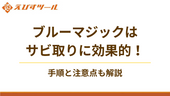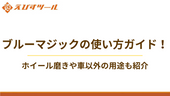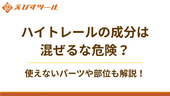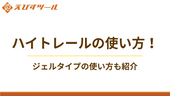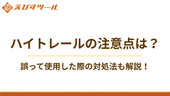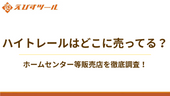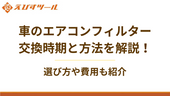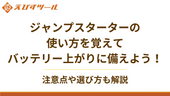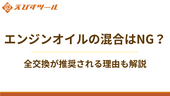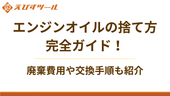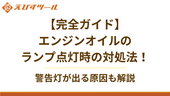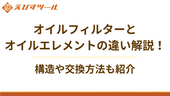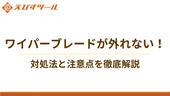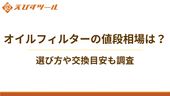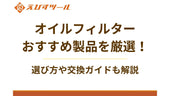ウォッシャー液は、雨やほこり、虫汚れなどで視界が悪くなったときにフロントガラスをきれいに保つために欠かせない存在です。しかし、いざ「ウォッシャー液を補充したい!」と思った際、どこに入れればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ウォッシャー液を入れる場所やタンクの見分け方、作業時の注意点や具体的な補充手順まで、初めての方でも安心してできるよう分かりやすく解説していきます。
ウォッシャー液の入れる場所は?

ウォッシャー液を正しく補充するための第一歩は、入れるタンク=ウォッシャータンクの場所を知ることです。ほぼすべての国産車・輸入車では、エンジンルーム(ボンネット内)に専用タンクが備わっており、キャップには特徴的なマークが記載されています。
間違った場所に注入するとトラブルや故障の原因となることもあるため、確実に見分ける方法を覚えておきましょう。
ウォッシャー液のタンクの見分け方
ウォッシャータンクは、主にボンネットを開けた際の左右どちらか端の位置に設置されていることが多いです。キャップ部分には「噴霧マーク」「ワイパー+水しぶき」のイラスト、または“WASHER”などの表記があり、給油口やラジエーターキャップと明確に区別できます。
タンクは半透明のプラスチック製で、中の液体の量が外からもわかる設計になっている車も多く、間違いを防げます。操作前に必ずキャップのマークや形状、周辺表示をよく確認しましょう。
【業界最安値を目指します】えびすツールの
ウィンドウォッシャー液はこちら
ウォッシャー液の補充時の注意点

ウォッシャー液の補充は手軽な作業ですが、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。特にタンクの間違いや補充方法、製品特性による取扱いの違いを理解して安全に作業を進めてください。
タンクを間違えないよう注意
エンジンルーム内にはいくつか似たようなタンクが存在します。エンジン冷却水用のラジエーターリザーバータンクやブレーキフルードのリザーバータンクなど、間違って他のタンクにウォッシャー液を入れると重大な故障になることがあるため、必ず「ウォッシャーマーク」を確認のうえ作業してください。
万が一迷った場合は取扱説明書で再確認をしましょう。
ウォッシャー液の「補充」と「交換」の違い
「補充」は足りなくなった分だけタンクに液を追加する作業、「交換」は一旦すべてのウォッシャー液を抜き取り、新しい液に丸ごと入れ替える作業を指します。
通常は補充で済みますが、違う種類のウォッシャー液同士が混ざることを避けたい場合や、長期間残っていた液が劣化している場合は、タンク内を空にしてから新しい液で満たす「交換」も有効です。
ウォッシャー液によっては薄めて使用するものもある
市販されているウォッシャー液には、薄めずそのまま使う“ストレートタイプ”と、希釈してから使う“濃縮(原液)タイプ”があります。濃縮タイプをそのまま注いでしまうとノズル詰まりや凍結の原因になることもあるため、パッケージの指示に従い所定の割合で水道水と混ぜてから補充しましょう。季節や気温に合わせて濃度を調整できるのも特徴です。
【業界最安値を目指します】えびすツールの
ウィンドウォッシャー液はこちら
ウォッシャー液の補充方法を解説

初めての方でも戸惑わずスムーズにできるよう、ウォッシャー液の補充手順を4ステップでご紹介します。注意点を押さえつつ作業すれば、短時間で安全に補充が可能です。
①ボンネットを開ける
まずは車のエンジンを止め、安全を確認したうえでボンネットを開けます。車内のレバーやスイッチでボンネットを解除し、しっかり固定しましょう。必ずエンジンが十分冷えた状態で作業するのがポイントです。
②ウォッシャータンクを探す
エンジンルーム内で「噴霧」や「ワイパーと水しぶき」のマーク付きキャップを探しましょう。周囲が汚れていて見づらい場合はキャップを軽く拭いて確認するのもおすすめです。外から中の液量が分かる車なら、合わせて液量チェックも行います。
③ウォッシャー液を補充する
キャップを開けて、タンクの規定ラインまでウォッシャー液をゆっくり注ぎます。高濃度タイプの場合は、必要に応じて水で所定の割合まで薄めてから注いでください。こぼさないよう注意し、補充が終わったらキャップをしっかり閉めてください。
④ウォッシャー液が出るか動作確認
補充後は必ず運転席に戻り、実際にレバーやスイッチでウォッシャー液が適切に噴射されるか動作確認を行いましょう。噴射されない場合はノズル詰まりや電装系トラブルの可能性も考え、再度点検を。正常に動けば作業完了です。
【業界最安値を目指します】えびすツールの
ウィンドウォッシャー液はこちら
ウォッシャー液の入れる場所は間違えないようにしよう
ウォッシャー液の入れる場所や見分け方、正しい補充手順は一度覚えてしまえばとても簡単です。ただし、タンクの種類を間違えたり、製品ごとの使い方を誤ると愛車のトラブルにつながる場合も。
本記事のポイントを参考に、定期的な補充や正しい管理を心がけて、いつでもクリアな視界で快適・安全なドライブを楽しみましょう。