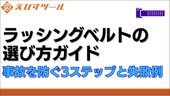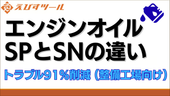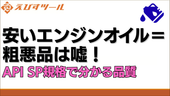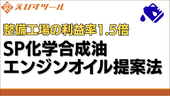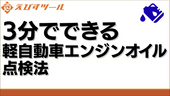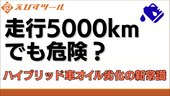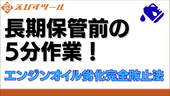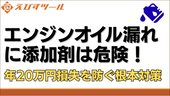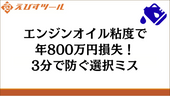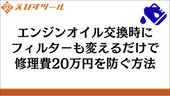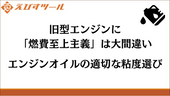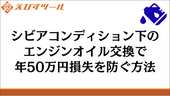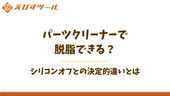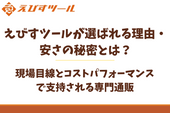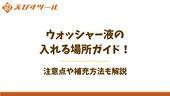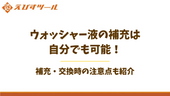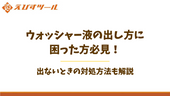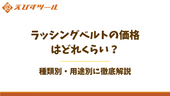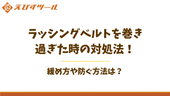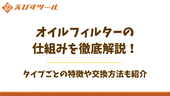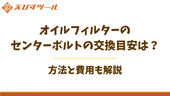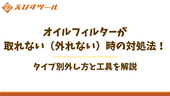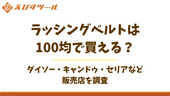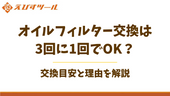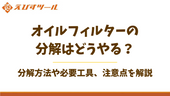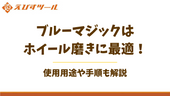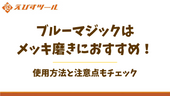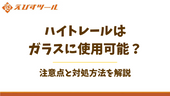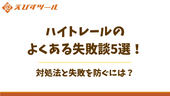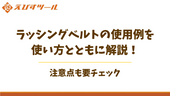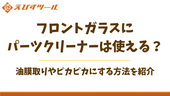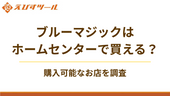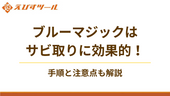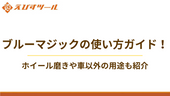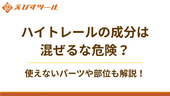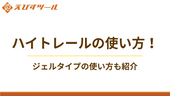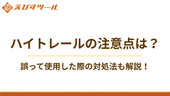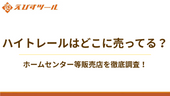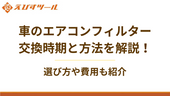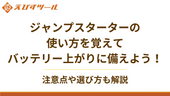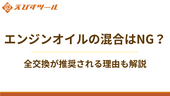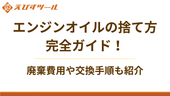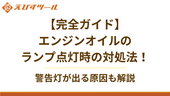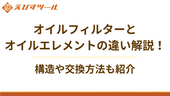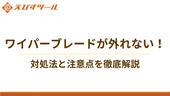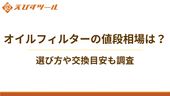運送業界を取り巻く環境は、年々厳しさを増しています。ドライバー不足、燃料費の高騰、そして配送エリアの拡大要請。こうした課題に日々向き合う中小運送会社の皆様にとって、「ドローン物流」という言葉を耳にする機会も増えてきたのではないでしょうか。
とはいえ、正直なところ「ドローンなんて大手企業の話で、うちには関係ない」と感じている経営者の方も多いはずです。実際、私たちが運送会社の担当者の方々とお話しする中でも、そうした声をよく耳にします。
本記事では、物流現場の実務者の視点から、ドローン物流が中小運送会社にとって本当に現実的な選択肢なのか、コストや実用性を含めて率直に検証していきます。同時に、ドローンに限らず今すぐ検討できる配送効率化の方法についてもご紹介します。
1. 中小運送会社が直面する配送の現実
1.1 深刻化するドライバー不足と採算性の悪化
2024年問題をきっかけに、運送業界の人手不足は一段と深刻になりました。トラック運転手の有効求人倍率は全職種平均の約2倍。求人広告にコストをかけても応募が来ない、あるいは採用してもすぐに辞めてしまう——こうした悩みを抱える企業が増えています。
さらに厄介なのが、採算の取れない配送依頼の増加です。過疎地域や山間部への配送は、1件あたりの単価では到底採算が合いません。それでも、長年のお客様からの依頼を断るわけにもいかず、結果的に赤字覚悟で配送を続けているケースも少なくないでしょう。
たとえば、こんな配送に心当たりはありませんか?
- 片道1時間以上かかる山間部への月数回の小口配送
- 緊急対応が必要な医薬品や工場部品の配送
- 都市部の渋滞で時間が読めない時間指定配送
こうした配送は、時間とコストがかかる割に売上につながりにくく、経営を圧迫する要因になっています。加えて、原油価格の高騰による燃料費、そして働き方改革に伴う適正な労働環境確保のための人件費上昇——。「配送の効率化」と「コスト削減」は、もはや待ったなしの経営課題です。

2. ドローン物流は本当に解決策になるのか?
2.1 ドローン物流とは何か
ドローン物流とは、無人航空機を活用して荷物を輸送する配送方法です。遠隔操作や自動操縦により、従来の車両では時間がかかっていたルートでも、空路を使って直線的に配送できる点が特徴です。
最近よく話題になるのが「ラストワンマイル配送」での活用。配送拠点から最終目的地までの区間を、渋滞や道路状況に左右されずに配送できるというものです。
2.2 中小企業に関係ある話なのか
結論から申し上げると、今すぐ全面導入を検討すべき段階ではありません。ただし、特定の配送ルートに限定して部分的に活用する可能性については、検討する価値があるケースも出てきています。
実際、国内でもいくつかの中小規模事業者が実証実験に参加しており、限定的な条件下では採算が取れる可能性が見えてきました。重要なのは「全てをドローンに置き換える」ではなく、「最も非効率な配送ルートをピンポイントで改善できないか」という視点です。
たとえば、1日に1〜2件しか配送がない山間部への配送のために、往復3時間かけてトラックを走らせている——このような明らかに非効率な配送こそ、ドローン活用を検討する余地があるといえます。

2.3 現時点での実用レベル
では、実際のところドローン配送はどこまで実用化されているのでしょうか。現状では、限定的な条件下での活用が中心です。
実用化が進んでいる領域:
離島や山間部への定期配送では、楽天が福岡県の離島で日用品や医薬品の配送を実施しており、地域インフラとして定着しつつあります。医療分野では、長野県や徳島県で検体・医薬品配送の実証実験が成功。災害時には、2024年の能登半島地震で道路が寸断された被災地への支援物資輸送でも活躍しました。
まだ難しい領域:
一方で、都市部での一般配送は航空法の制約や安全性の観点から実用化のハードルが高く、現行機種は積載重量5kg以下が主流のため大型荷物には対応できません。悪天候時も、風速7m/s以上になると飛行困難になります。
つまり、ドローン物流は「万能の解決策」ではなく、あくまで「特定の配送課題に対する選択肢の一つ」として捉えるべきでしょう。

3. 中小企業でも参考になる導入事例とコスト試算
3.1 実際の導入事例
ここでは、実際にドローンを導入した中小規模事業者の事例をご紹介します。
事例1:山間部の温泉宿への配送(長野県)
地元の運送会社が、山間部の旅館へ食材を配送するためにドローンを試験導入。往復2時間かかっていた配送が20分で完了し、ドライバーの拘束時間が大幅に削減されました。この事例の興味深い点は、天候が良く軽量な荷物の場合のみドローンを使う「使い分け」を実践していることです。
事例2:離島への医薬品配送(長崎県)
フェリーの運航本数が限られる離島への緊急配送に、地元企業がドローンを導入。初期投資は約200万円でしたが、緊急配送の依頼が増加し、月間売上が15%向上したとのことです。
3.2 リアルなコスト試算
「で、実際いくらかかるの?」——これが一番気になるところではないでしょうか。中小運送会社がドローンを導入する場合の、現実的なコストを試算してみました。
| 項目 | 初期コスト | 月額ランニングコスト |
|---|---|---|
| 産業用ドローン機体 | 150〜300万円 | - |
| 操縦ライセンス取得 | 15〜30万円/人 | - |
| 保険・メンテナンス | - | 5〜10万円 |
| 運航管理システム | 50万円 | 3〜10万円 |
| 合計 | 約215〜380万円 | 約8〜20万円 |
決して安い投資ではありません。ただし、リースを活用すれば初期投資を月額10〜20万円程度に抑えることも可能です。自治体によっては導入補助金を用意しているところもあり、1日2〜3便以上の定期配送がある場合、採算ラインに乗る可能性があります。
3.3 費用対効果が見込めるケース
では、どんな配送ならドローン導入を検討する価値があるのでしょうか。以下の条件に複数当てはまる場合は、一度真剣に検討してみる価値があるかもしれません。
- 配送先まで片道30分以上かかる
- 荷物の重量が3kg以下
- 週3回以上の定期配送がある
- 配送単価が1件3,000円以上取れる
- 飛行ルートに障害物が少ない(山間部・海上など)
逆に言えば、これらの条件に当てはまらない場合は、まだドローン導入を急ぐ必要はないでしょう。

4. 導入前に知っておくべき課題と規制
導入を検討する前に、現実的な課題についても正直にお伝えしておく必要があります。
4.1 航空法の制約
ドローンの飛行には、航空法による厳しい規制があります。人口集中地区(DID地区)での飛行、人や建物から30m未満の飛行、夜間飛行・目視外飛行などでは、国土交通省への申請・許可が必要です。
申請手続きは慣れていないと複雑で、書類作成だけで数日かかることも。現実的な対応策としては、行政書士などの専門家に申請代行を依頼する方法があります(費用相場5〜10万円程度)。
4.2 技術的な制約
バッテリー寿命の問題: 現行ドローンの飛行時間は20〜40分程度。往復の配送距離は10〜15kmが限界です。「思ったより飛べない」というのが、多くの事業者が最初にぶつかる壁です。
天候に左右される: 風速7m/s以上、降雨時、濃霧時は飛行できません。そのため、ドローン配送を導入する場合でも、必ずバックアッププラン(通常の車両配送)を用意しておく必要があります。
4.3 安全対策
万が一の墜落や衝突に備えて、賠償責任保険への加入(必須)、緊急着陸地点の事前設定、定期的な機体メンテナンス、悪天候時の運航中止基準の明確化が不可欠です。特に保険については、事故で第三者に被害が及んだ場合、賠償額が数千万円に及ぶケースもあるため、必ず加入しておきましょう。

5. 今すぐ検討できる現実的な配送効率化
ここまで読んで「やっぱりドローンはまだ早いかな」と感じた方も多いのではないでしょうか。実際、多くの中小運送会社にとって、ドローンは「将来の選択肢」として頭の片隅に置いておく程度で良いと思います。
それよりも、今すぐ取り組める配送効率化の方法を検討する方が現実的です。
5.1 配車システムの見直し
AIを活用した配車最適化システムは、無駄な走行距離を20〜30%削減できたという事例が実際に報告されています。月額数万円から始められるサービスもあり、ルートの最適化だけでなく、ドライバーの労働時間管理や燃費データの一元管理もできるため、コンプライアンス面でも役立ちます。
5.2 共同配送の推進
「競合他社と手を組むなんて」と思われるかもしれませんが、近隣の同業者とエリアごとに配送を分担する動きは全国で広がっています。業界団体や自治体が音頭を取って、マッチングサービスを提供しているケースも増えてきました。
5.3 デジタル化による業務効率化
配送管理や車両管理をデジタル化するだけでも、事務作業の負担は大幅に軽減できます。紙ベースの配車表や日報から脱却するだけで、月間で数十時間の工数削減につながったという声もよく聞きます。
こうした「地に足のついた」業務改善を支援する企業として、私たちえびすツールがあります。
えびすツールは、運送会社の現場を長年見てきた専門家が運営するECサイトです。扱っているのは、大手企業向けの高額なシステムではありません。中小運送会社が日々の配送・荷役作業で実際に使う、ラッシングベルト、スリングベルトといった荷物の固定・積載に欠かせない資材を、現場目線で厳選しています。
荷物を安全に固定するラッシングベルト、重量物の吊り上げに使うスリングベルトなど、物流現場で毎日使う消耗品や機材こそ、品質とコストパフォーマンスが重要です。えびすツールは、そうした現場の声に応える商品だけを取り扱っています。
ドローンのような最先端技術ももちろん重要です。でも、それ以上に大切なのは、日々の業務を着実に改善していくこと。派手さはなくても確実に効果が出る——そんな「堅実な業務改善」こそが、中小運送会社の持続的な成長につながると、私たちは考えています。

6. まとめ:今、中小運送会社が取るべきアクション
ドローン物流との向き合い方
ドローン物流は、確かに物流業界の未来を変える可能性を持った技術です。ただし、中小運送会社にとっては「今すぐ全面導入すべき技術」ではなく、「特定の配送課題に対して、条件が整えば部分的に活用を検討する選択肢」として捉えるのが現実的でしょう。
むしろ大切なのは、自社の配送業務の現状を正確に把握し、本当にドローンが必要なのか、それとも他の方法で解決できるのかを見極めることです。
今すぐできること
まずは以下のステップから始めることをお勧めします。
- 自社の配送データを分析し、非効率なルートや時間帯を洗い出す
- 配車システムや管理ツールなど、小規模なデジタル化から始める
- 自治体の補助金・助成金の情報を収集しておく
- ドローン規制の緩和や技術進化については、継続的にウォッチしておく
ドローン技術は日進月歩で進化しています。5年後には、今よりはるかに導入しやすくなっている可能性が高いでしょう。今は「情報収集と準備の時期」と捉え、将来の選択肢を広げておくことが賢明です。
配送効率化に特効薬はありません。ドローンのような最先端技術も、配車システムの改善も、共同配送も、それぞれが一つのピース。複数の改善策を組み合わせて、自社に合った形を作っていくことが大切です。
えびすツールは、日々の荷役作業を支える資材を通じて、運送会社の皆様の「地道だけれど確実な業務改善」を支援するパートナーでありたいと考えています。最先端技術に目を向けつつも、足元の業務改善をおろそかにしない——このバランス感覚こそが、これからの中小運送会社に求められる姿勢ではないでしょうか。
参考リンク:
- ラストワンマイル物流とは?|行政書士法人シフトアップ
- 国土交通省 無人航空機の飛行ルール